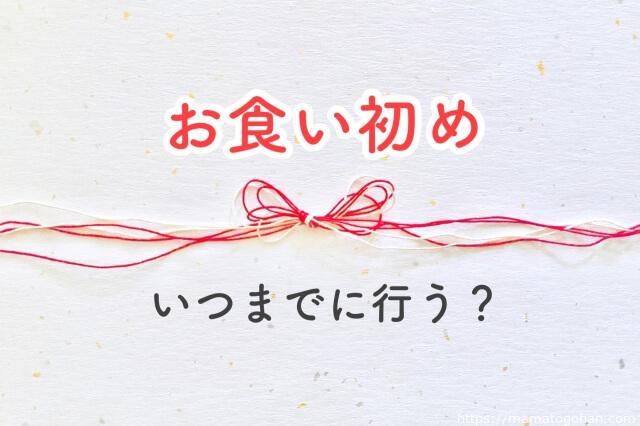<景品表示法に基づく表記>この記事には広告を含む場合があります。パートナーの意見は評価には影響しません。
当記事ではお食い初めはいつ行うのかを解説しています。
赤ちゃんの生後100日をお祝いするお食い初めは、生後100日前後で行われる事が多いですが、厳密に100日目である必要はありません。
![]() マチ子
マチ子
お食い初めはいつ行うのか、100日の数え方を含めて詳しく解説します。
以下のような細かい疑問にもお答えします。どうぞご参考ください。
 自宅で生後100日の「お食い初め」手作りメニューで簡単にお祝いするヒント5つ
自宅で生後100日の「お食い初め」手作りメニューで簡単にお祝いするヒント5つ
お食い初めはいつ行う?【計算方法】

お食い初めは赤ちゃんの生後100日をお祝いする儀式なので、生後100日前後で行うのが一般的です。
地域によっては、110日や120日の吉日に行われます。
どの場合であっても、生後100日ぴったりでなければならないという厳密な決まりはありません。
赤ちゃんやママの体調を優先し、家族が集まりやすい日取りでお祝いしましょう。
日本の伝統的な数え方では生まれた日を生後1日目としてカウントします。
100日目を計算するにはこちらのサイトが便利です。▼
生年月日を入力すると、お七夜〜成人式までの日付を自動で計算してくれますよ
生後100日以降はいつまでお食い初めができる?
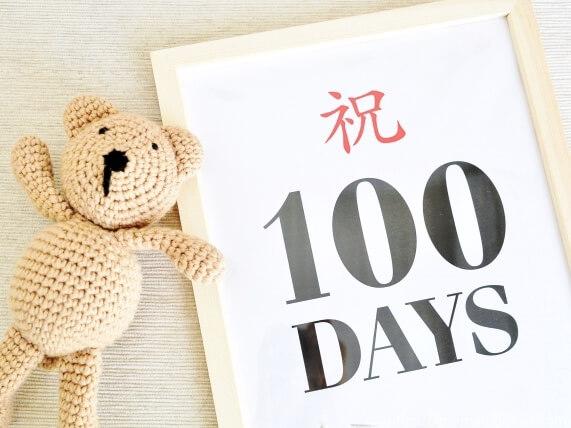
お食い初めは生後100日過ぎた後もお祝いすることができます。
近畿地方では、あえて日付を送らせることで、「食い延ばす」=「長生きする」という縁起を担ぐ文化もあるようです。
- お正月
- 初節句(端午の節句・桃の節句)
- ハーフバースデー
生後100日を過ぎていて、他のイベントが近いのであれば同時に行うことも可能です。
期限はありませんが、「食べるものに困らないように」と願う儀式なので、離乳食が始まる6ヶ月頃までが1つの目安になります。
お食い初めは大安が良い?仏滅はだめ?
| 六曜 | 午前 | 正午 | 午後 | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 大安 | 何事にも吉日。 | |||
| 友引 | 祝い事には吉。 | |||
| 先勝 | 午前中開始は吉。 | |||
| 先負 | 正午以降なら吉。 | |||
| 赤口 | 11時〜13時は吉。 | |||
| 仏滅 | 全てに凶日。 |
中国の陰陽五行説に由来する「六曜」では、6つの曜があります。
最も縁起が良いのは大安で、仏滅は何を行うにも不吉で縁起が悪いとされています。
現代ではそれほど気にする必要はないという考え方が一般的です。
仏滅は、元々の表記が「物滅」であることから「新たな物事を始めるのに適した日」という解釈もあります。つまり意味合いは考え方次第といえます。
お食い初めの日取りは、パパママが気にしないのであれば仏滅でも問題なし。家族の中に気にする人がいるなら、考え方を尊重するのが無難といえるでしょう。
2022年の六曜はこちらのカレンダーでチェックできます。▼
お食い初めに向いている時間帯は?

お食い初めを行う時間帯は、赤ちゃんが起きている機嫌の良い時間帯がベストです。
お食い初めは赤ちゃんに食べ物を食べさせる真似をする儀式なので、グズグズタイムだとちょっと大変。空腹時も避けたほうがいいでしょう。
赤ちゃんのご機嫌な時間帯や体調をみて判断してみましょう。
記念撮影をするのであれば、自然光の入る日中は明るく綺麗に写りますよ。
我が家は授乳を済ませてご機嫌なお昼時を選びました
お食い初めは早めにやってもいい?

お食い初めを生後100日以前に行うのはおすすめできません。
理由は以下の通りです。
- 赤ちゃんの首がすわっていない
- ママの体が回復しきっていない
- 赤ちゃんのいる生活に慣れていない
赤ちゃんの首がすわるのは生後3〜4ヶ月頃です。
首がすわっていない状態だと、抱っこするとしても不安定で、赤ちゃんの体に負担がかかってしまいます。
また、慣れない育児に追われながらイベントの準備も、となるとつらく感じてしまうかもしれません。
気持ちに余裕をもって行うのであれば、100日以降がベストです。
上記で述べた通り遅らせてお祝いする分には全く問題ありませんよ。
お食い初めはお宮参りと同時にやってもいい?

お食い初めとお宮参りは同時に行うことができます。
近年、遠方の親族の集まりやすさから一緒に済ませる家庭も増えてきました。
以下のようなメリットがあります。
- 親族が集まりやすい
- 赤ちゃんとママの体調に余裕ができる
- 食事会などの費用が抑えられる
- イベントが1度で済む
お宮参りは生後1ヶ月頃が目安になりですが、同時に行う場合は、お宮参りの日程を送らせて生後100日頃に合わせましょう。
お食い初めの準備はいつから?やるべきこと3つ

お食い初めの準備は、生後2ヶ月頃から考え始めるとスムーズです。
やるべきことは主に3つあります。
- 招待する人数を決める
- 日取りを決める
- 食事会の準備をする
自宅で行う場合と、レストランや料亭で行う場合では、準備の内容が異なります。
以下で詳しく解説します!
その①招待する人数を決めよう
お食い初めは両親だけで行うことができますが、両家の祖父母を呼んでお祝いする家庭も少なくありません。
誰を呼ぶのか、お食い初めの参加人数を決めましょう。
可愛い赤ちゃんの行事は、誰でもお祝いしたいと思うもの。気持ちのすれちがいがおきてしまわないように一声かけておくと安心です。
その②日取りを決めよう
人数が決まったら家族が集まりやすい日取りを相談します。
- 平日より土日がいい
- 縁起の良い大安を選びたい
- 1月は寒そうだから4月に延期しよう
ご家族の生活スタイルに合った日を選んでくださいね。
その③食事会の準備をする
お食い初めの儀式には、お食い初め専用の料理「お祝い膳」が必要です。
儀式の後は、用意した料理を家族で食べるので食事会という形になります。
外食と自宅では準備内容が異なります。以下をご参考ください。
1ヶ月前に人数分の予約を取る。
大安・土日から予約が埋まっていくのでお早めに。
料理・食器・お箸・歯固め石を用意する。
通販で注文するものを決める。
自宅でお食い初めをする場合、料理は必ずしも手作りしなければならないというわけではありません。
通販のお食い初めセットを利用すると、お食い初め準備の負担が軽減されますよ。
お食い初め料理を通販したい方は「お食い初めセットランキング」の記事をご参考ください。
 お食い初めセット通販・宅配で人気ランキング!おすすめ9選
お食い初めセット通販・宅配で人気ランキング!おすすめ9選
お食い初めは生後100日を過ぎても大丈夫
お食い初めはいつ行うものなのかを解説しました。
お食い初めは生後100日過ぎてからでもお祝いできます。焦る必要はありません。
準備は生後2ヶ月頃から始めると当日がスムーズに迎えられます。
ご家族に無理のない日取りで楽しいお食い初めにしてくださいね。